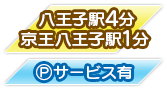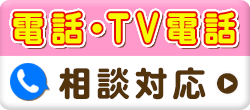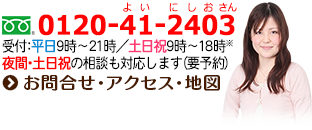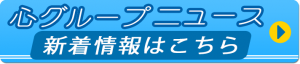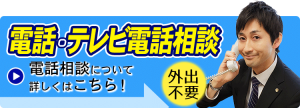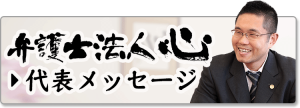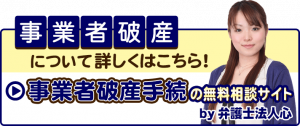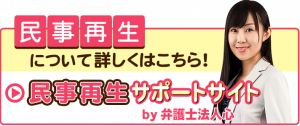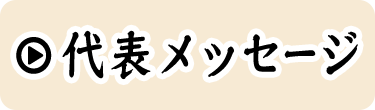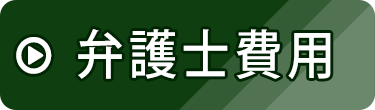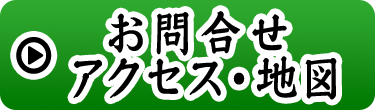法人破産できないケースとは
会社の経営には、従業員や取引先など多くの人々や企業が関わっています。
もし会社が破産するとこれらの関係者に大きな影響を及ぼすため、破産法には破産をするための条件が詳細に定められています。
つまり、資金繰りが悪化し「会社を破産させよう」と思っても、破産法に定められた条件を満たさない限り法人破産はできないのです。
以下、法人破産ができない場合について説明します。
なお、会社とは株式会社などの「法人」を指しますが、平易な表現とするため、この記事では「会社」と表記します。
1 破産手続開始原因が存在しない
会社が破産を申し立てると、裁判所はまず、手続きを「開始」するための「原因」(破産手続きの開始原因)があるか否かを審査します。
破産法は、破産手続きの開始原因として「支払不能または債務超過」という条件を定めています。
⑴ 支払不能
支払不能とは、「債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的、継続的に弁済することができない状態」と定義されています(破産法2条11項)。
平易な表現をすれば、「約束の支払い日に支払いができず、おそらくその先も支払いができない」という状態です。
たとえば、「現時点で現預金が足りないため、今月末の支払い日には支払いができないが、来月初めに納品予定があり、その代金が入金されれば支払いができる」という場合には、支払不能とはいえません。
一時的に資金繰りが厳しいだけである場合は、「一般的、継続的に弁済することができない状態」とまではいえないからです。
もちろん、約定の返済が滞ると、事実上会社の信用に影響は生じることもありますが、それだけで直ちに「支払不能」とはならないのです。
一方で、「この商品は近い将来、爆発的にヒットするので、多額の売り上げが見込める」と確信していたとしても、現実的に売り上げがなく、支払いができる見通しが立たない状態であれば、その会社は「支払不能」といえるでしょう。
また、「今は支払えないが、営業を継続していずれは支払う」という意思があったとしても、会社が支払を停止したといえる状況にあれば、「支払不能」だと推定されます。
例えば、弁護士に債務整理を依頼して債権者に支払停止の通知をした場合や、営業していた店舗をすべて閉鎖した場合などは、一般的に会社が支払を停止した事実を外部に表明する行為であると考えられるため、「支払不能」の状態にあると推定されます。
⑵ 債務超過
債務超過とは、「会社の財産をもってしても債務を完済できない状態」をいいます(破産法16条1項)。
会社の貸借対照表が債務超過であれば、破産法上も債務超過ということになります。
債務超過については、客観的な数字で判断できるので分かりやすいでしょう。
なお、債務超過とは、「会社の財産で債務を支払えるかどうか」が問題なので、仮に代表者の財産を投入すれば債務を支払えるとしても、会社の財産で支払えなければ債務超過です。
2 破産障害事由がある
破産手続きの開始原因(支払不能または債務超過)があったとしても、次のような破産障害事由(破産手続を始めることができなくなる事由)がある場合には、破産は認められません。
⑴ 破産手続の費用が用意できない
弁護士に依頼して裁判所に破産を申し立てる場合には、弁護士費用がかかりだけではなく、裁判所に「予納金」を納めなければなりません。
裁判所に破産を申し立てても、予納金が納められなければ、破産手続き開始決定はなされません。
予納金の額は、負債額や債権者数、事案の内容によって裁判所ごとにある程度異なり、数十万円~数百万円になります。
⑵ 破産申立ての目的が不当・不誠実
誠実に努力した結果、会社の経営が立ち行かなくなり、破産を申し立てるのは仕方がないことです。
しかし、不当・不誠実な目的で破産を申し立てると、破産は認められません。
例えば、新しい会社を設立し、現行会社の資産や得意先など良い部分のみを新会社に無償で移転して新会社にて営業を継続しようと画策し、負債のみが残った現行会社を破産させ債務を免れようとの意図で破産を申し立てるのは、不当・不誠実な破産であると判断される可能性が高いと考えられます。
もっとも、「会社の経営が苦しくなり、収益の柱を作ろうとして新規事業を始めたり、追加融資を受けたりしたが、結果的に破産を申し立てるしかなくなった」ということもあります。
このような場合に、債権者や取引先に迷惑をかけたからといって、直ちに不当・不誠実と評価されるわけではありません。
3 申立ての権利者の問題
破産の要件のなかでも重要なものである「申立ての権利者(申立権)」について説明します。
会社の場合、「誰に破産を申し立てる権利があるのか」という点が問題となることがあります。
申立ての権利者が申立てをしないと、当然、申立ては適法とされません
法人破産は、会社の経営が立ち行かなくなり、社長が苦渋の決断で破産を申し立てる、というのが典型的なイメージであるかと考えられます。
しかし、会社の経営者は社長1人だけとは限りません。2~3人以上の取締役がいる会社も多く存在します。
そこで、3人の取締役がいる取締役会設置会社が破産を申し立てようとしているケースを例に考えてみます。
破産を申し立てるには、原則として取締役会の決議が必要になります。
会社が破産を申し立てるときは、破産申立書に「破産申立てすることを決定した」という内容の取締役会議事録を添付します。
取締役会で3人の取締役全員が破産申立てに賛成すれば、満場一致ですから何ら問題はありません。
もし、3人のうち1人が破産申立てに反対しても、過半数の賛成があるので、破産申立てが可能です。
しかし、3人の取締役のうち2人が反対し、議案が否決された場合はどうでしょうか。
この場合は、会社の自己破産はできません。
しかし、「これ以上営業を続けるとかえって取引先に迷惑をかけるので破産する方が良いのは明らかなのに、反対意見ばかりだ。」「他の取締役と連絡が取れなくなってしまった。」という場面も現実的には考えられます。
そのような場合には、取締役1人だけでも破産を申し立てることができる旨を破産法が定めています。
これを「準自己破産」といいます。
【債権者破産】
実は、債権者(お金を貸している側)にも破産を申し立てる権利があります。
これを「債権者破産」と言います。
「債権者が破産を申し立てて何の得があるのか」と不思議に思うかもしれませんが、会社を清算することだけが破産の目的ではありません。
破産の本来の目的のひとつは、会社に残った財産を債権者に公平に分配することです。
債務者に多額の融資をしている債権者が、「もはや債務者の経営が立ち直る見込みはない。このまま今の社長に放漫経営を続けさせていては、1円も回収できなくなる。早めに破産手続を行なえば、多少なりとも配当を受けられる可能性がある」と考えた場合には、債権者が破産を申し立て、破産手続きによって、債務者の財産から配当を受けるのです。
実際に、銀行などの金融機関が債権者破産を申し立てるケースもあります。
4 法人破産できないか不安な方は弁護士へご相談を
会社が破産すると、取引先や従業員に大きな影響を与えるため、会社の経営が悪化した時点でできるだけ早く対応を考えることが大切です。
状況が悪化するほど取引先や従業員に迷惑を掛けてしまう可能性が高くなりますし、さらには、破産申立てに必要な費用を用意することすら困難であるという状況にも陥りかねません。
もし、「会社を破産させるべきかどうか」「そもそも自分の会社は破産できるのだろうか」などのお悩みをお持ちであれば、できるだけお早めに当法人へご相談ください。
個人だけでなく、会社の破産についても経験豊富な弁護士が、手続き開始から終了まで対応いたします。